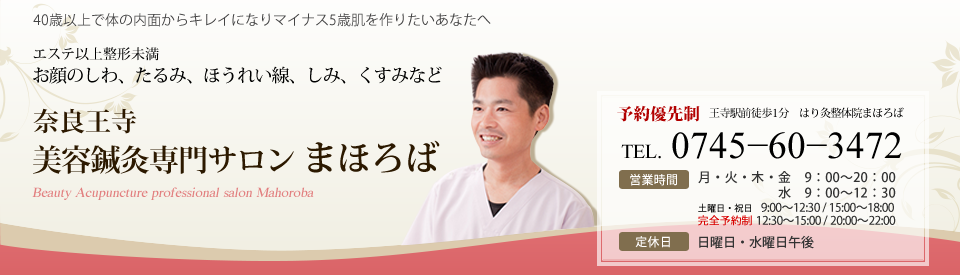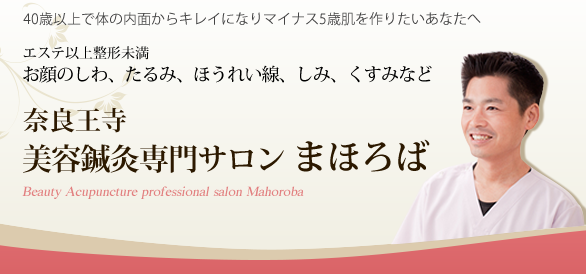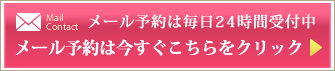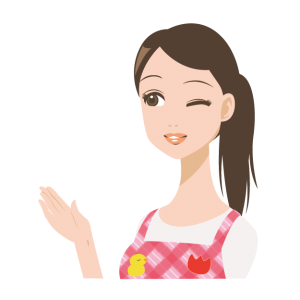こんにちは。
4月も中旬に入り、春の日差しも強くなり
温かい日も多くなってきました。
本日は美容の大敵であるシミやシワの元となる活性酸素についてと
その予防によい春の野菜をご紹介したいと思います。
私たち人間が生きるうえで絶対に欠かすことができない酸素は
すべてが生命維持のエネルギー源だけに使われるわけではなく、
一部「活性酸素」というものに変化します。
この活性酸素は増えすぎると酸化の原因にもなってしまいます。
酸化とはリンゴやじゃがいもを長時間放置すると変色したり、鉄が錆びるように
ある物質が酸素と化合したときに起きる反応のこと。
実は私たち人間の体内にも同様のことが起きているのです。
体が酸化すると正常に機能しない細胞が増え、代謝が滞り、
これが長期に及ぶとさまざまな不調が現れ始めます。
老化を早めたり、お肌や毛髪への影響や生活習慣病 等
さらには三大疾病にまでつながる可能性さえあります。
酸化に抗う、抗酸化力の高い栄養成分はビタミンA,C.E,亜鉛
などが挙げられます。
ビタミンAは目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、活性酸素の
攻撃から体を守ってくれます。
紫外線は活性酸素が増える原因のひとつでシミ、シワ、たるみといった
美容のお悩みのもとですが、ビタミンAは皮膚の正常化を
助ける働きがあります。
主な食材は、にんじん、かぼちゃ、ホウレンソウ、うなぎ、鶏レバー、etc
ビタミンCは活性酸素を無害化して、細胞の酸化を防ぐ力があります。
ただしビタミンCは体内に残りにくく、2,3時間程でなくなってしまう短所が
ありますので、こまめに摂取する必要があります。
主な食材はレモン、イチゴ、キウイ、パセリ、芽キャベツ、ピーマン、ジャガイモetc
ビタミン Eは過酸化脂質の発生を抑える働きがあります。
過酸化脂質とはコレステロールや中性脂肪が酸化したもので、
いわゆるドロドロ血液の状態です。
主な食材はブロッコリー、アボガド、いくら、たらこ、オリーブオイル、ナッツ類etc
亜鉛は味覚を正常に保ち、皮膚の傷の回復を早めてくれ、
抗酸化物質の働きを助け、その効果を高めます。
主な食材は牡蠣、ホタテ、高野豆腐、牛もも肉、豚レバー etc
体のサビに抗う抗酸化力はもともと人体に備わっているもの。
その力は40歳頃から顕著に低下します。
抗酸化力の高い栄養成分を知り、それらを多く含む食材を
バランスよく摂取することが一番の対策と言えるでしょう。