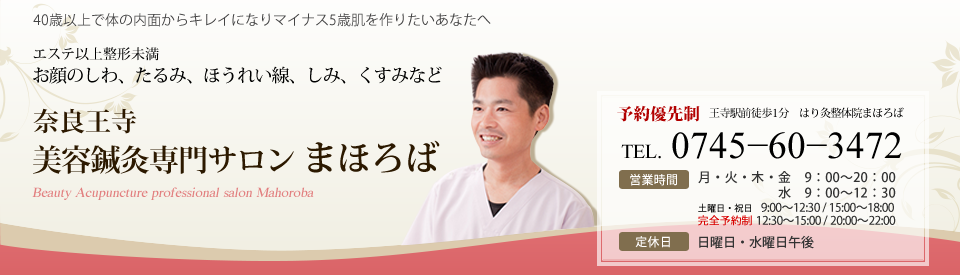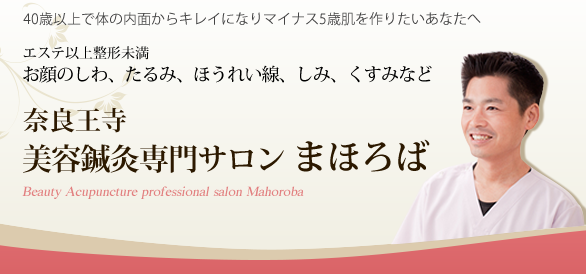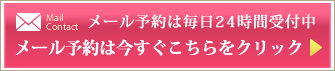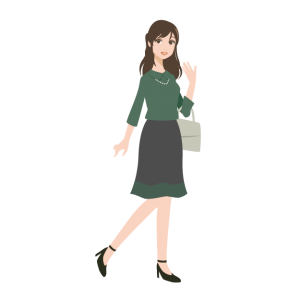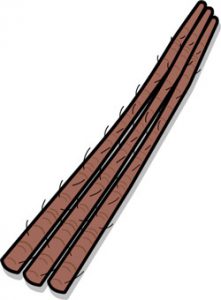肌タイプによる日焼け止めの使い分けと紫外線対策
こんにちは。
今年は猛暑日が続き、暑い日が続きますね。
さて、外に出る時は紫外線対策をしていると思いますが、
日焼けをするとお肌が赤くなる人や黒くなる人がいるように
それぞれの肌タイプによって、日焼け止めを選ぶ種類を変えなければなりません。
本日はお肌を3つのタイプに分類してお伝えします。
紫外線に当たると、、、
1・すぐ赤くなるが、黒くはならないタイプ
メラニン(紫外線からお肌を守る黒い色素)をつくるメラノサイトの働きが弱いタイプ。
SPFやPAの数値の高い日焼け止めで対策をしましょう。
◎SPFとは、短時間でお肌に赤みや炎症を起こさせ、黒化に
つながりやすくなるUV-B(紫外線B波)を防ぐ効果指数のこと。
しわやたるみの原因のひとつ。
SPFは50⁺が最高値です。
PAとは、一時的な黒化を引き起こし、長時間かけてお肌の
弾力を失わせるUV-A(紫外線A波)を防ぐ効果指数のこと。
PAは++++が最高値です。
紫外線に当たると、、、
2・赤くなって、そのあと黒くなるタイプ
日本人に最も多いタイプ。
散歩や買い物ならSPF10前後で、PA+。
庭仕事やスポーツ観戦ではSPF20前後で、PA++。
海水浴や山歩きではSPF30前後で、PA+++がおすすめ。
紫外線に当たると
3.赤くならずにすぐ黒くなるタイプ
紫外線への抵抗力は高いものの、メラノサイトの活動が盛んなタイプ。
紫外線対策はもちろん必要ですが、SPFやPAの数値はそれほど
高くなくてもOKです。
以上、ご自分の肌タイプによって、日焼け止めの使い方をお伝えしましたが、
さらに以下の3つの注意でお肌を守れます。
1・時間、場所
1日のうちで紫外線量が最も多いのは午前10時から午後2時頃です。
この時間帯の外出はできるだけ控え、外出の際はひさしのあるところや
木陰などを選んで歩き、直射日光を避けましょう。
室内でも日当たりの良い場所は要注意です。
2・日傘、帽子で髪も守る
お肌と同様に紫外線の影響を受けやすいのが髪です。
紫外線は髪のタンパク質を切断してパサパサのダメージヘアにしてしまいます。
お肌だけでなく髪もしっかり守りましょう。
3・睡眠
基本中の基本ですが、睡眠ほど大事なものはありません。
細胞の新陳代謝を促し、お肌のダメージを修復する成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。
特に多く分泌されるのが眠り始めてから約3時間の深い眠りのとき。
寝る前はカフェインを含むコーヒーやお茶は控えましょう。
記録的な猛暑が続いてますが、工夫してお肌を守りましょう。